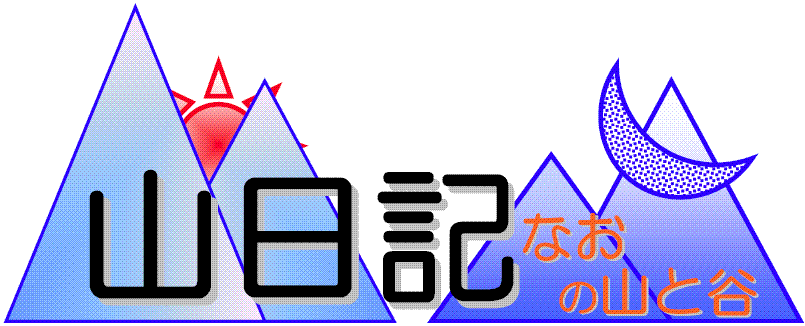
【TITLE】道標( Like a Werter/Die Leiden des jungen Naomi's )
【DATE】1996年12月
【MEMO】Piolet No.337掲載
今年も冬がやって来る。
ついこの前までは事務所に入りきらないくらい例会に集い、山行に参加していた会員が、雪の知らせとともにどこかへ消えていく。いつものこの光景が今年も繰り返されるのだろうか・・・
私が山を始めたのは18の頃だった。大学に入ったものの、心の中に何だかポカンと大きな穴があいてしまったかのように漫然とした日々を送り、いわゆる5月病というやつになった時のことだ。なんだかよく分からない日々を送り、なんだかよく分からない探検部とかいう部室に足を踏み入れたのがきっかけだった。
探検部は山から始まり、川下り、洞窟、無人島、チャリンコ、ダイビングとアウトドア的な物は何でもござれの何だかよく分からない会だった。しかし、その時私にやさしく説明してくれた女の先輩が、女神に見え、これで私は救われたのだと密かに思ったのだった。
動機が不純であったこともあるが、当時の私は山が嫌いだった、ヒーヒーゼーゼーと苦しい思いをして山に登って何が楽しんだと、また、山=死という印象も強く、どうしても好きになれなかった。また、高校山岳部出身の同期がおり、山のことは俺が一番知っているとばかりにしたり顔で山のことを語るその姿も好きになれなかった。だから、山をやりたい奴は山岳部にでも行け、俺達は探検部だと、川下り、洞窟、無人島などに自分の生きる道をはめ込み、たいして探検的なこともやっていない割に偉そうなことを吠えていた。
そんな私を少しばかり変えたのは、縄文の遥かなら時代からある白神の偉大なる大自然、母なるブナの森であった。沢づたいに尾根を越え、4日かけて白神山地を横断して日本海に抜けるという計画は、私にはただ辛いだけの山行で、当然私はメンバーに入っていなかったのだが、ひょんなことから参加することとなった。そして沢登りというものに出会ったのだった。
白神の自然と戯れるのは沢登りが一番だった。沢は何といっても変化に富んでいた。大滝、小滝、淵、ゴルジュ、釜、緑と青のコントラスト。沢には岩魚が泳ぎ、そしても僕も泳ぐ。でも岩魚には勝てない。夜には空を焦がさんばかりの大きな焚き火の周りで満点の星空を眺め、パーポンを片手に愛と人生と夢を語る。これ以上の至福はなかった。
しかし、私が好きだったのは白神の森であり沢であった。どうして苦しい思いをして尾根を登ったり、寒さにうち震えながら雪山を登ったりする必要があっただろうか。ましてや岩登りなんて論外だった。
いつまでも学生をしていられる訳はなく、やがて社会人になった。道南の小さな港町で組織という大きな歯車のひとつとして、現実の社会に埋もれて行く自分がそこにいた。
学生の頃の自分を思った。時には優しく時には荒々しい、創造と破壊の両面をもったあの偉大なる大自然と対峙し、再び自分を確認したいと思った。そして決めた。沢登りを通じてまたあの頃の何かを取り戻そうと。私は函館の社会人山岳会の門を叩いた。あれから5年の月日が流れ、今、私はPioletにいる。
基本的に自然と戯れたいという気持ちに変わりはない。源は白神に初めて入り、沢を楽しんだあの頃の気持ちと変わらない。しかし、今の自分は多くのことを学び、感じた。あの頃の自分はただ知らなかっただけだった。扉を開き、そこに足を踏み入れることを躊躇しているだけだった。
単に焚き火の周りで踊っているだけが沢じゃない。格闘しながら函や滝を突破して、ピークにたった時のあの充実感はいったい何なのだろう?ただ苦しいだけが尾根歩きじゃない。大雪や日高のあの雄大で長大な太古からの息吹を感じさせるものは何なのだろう?ただ寒くてつらくて眠れずに震えるだけが冬山でない。あの凛とした静寂の中に美しくそびえる白き峰々の美しさは何なのだろう?真っ白なキャンバスに思い思いのシュプールを描き、雪煙をあげながら" Oh Schi Heil ! "この浮遊感は何ナノか?「何が面白くて垂直の世界を、命が幾つあったて足りない」と言っていた自分がまさか凍った滝を登ったり、岩を登るためだけに隣の国に行くと10年前の自分に想像すらできなかった。
私はただ知らなかっただけだった。足を踏み入れようとしなかっただけだった。山の世界がこんなに広く奥深いもので、知識・経験・技術・経験を積むことにより、これほどまでにゾクソクする充実感、自然の創造性と破壊性、その雄大さ、奥深さ、そして自分の生・存在を感じさせてくれるものはない。
誰もが初めは素人。誰もが初めはわからないから、勝手な自分の思いこみで、新しい世界の扉を開こうとしない。決めるのは少しでも足を踏み入れてから、経験してからでも遅くはない。明日のあなたは何を思っているかわからない。明日の違う自分に出会うために目の前の扉を開いてみよう。そして一歩踏み入れてみよう。
今年も冬がやって来る。

